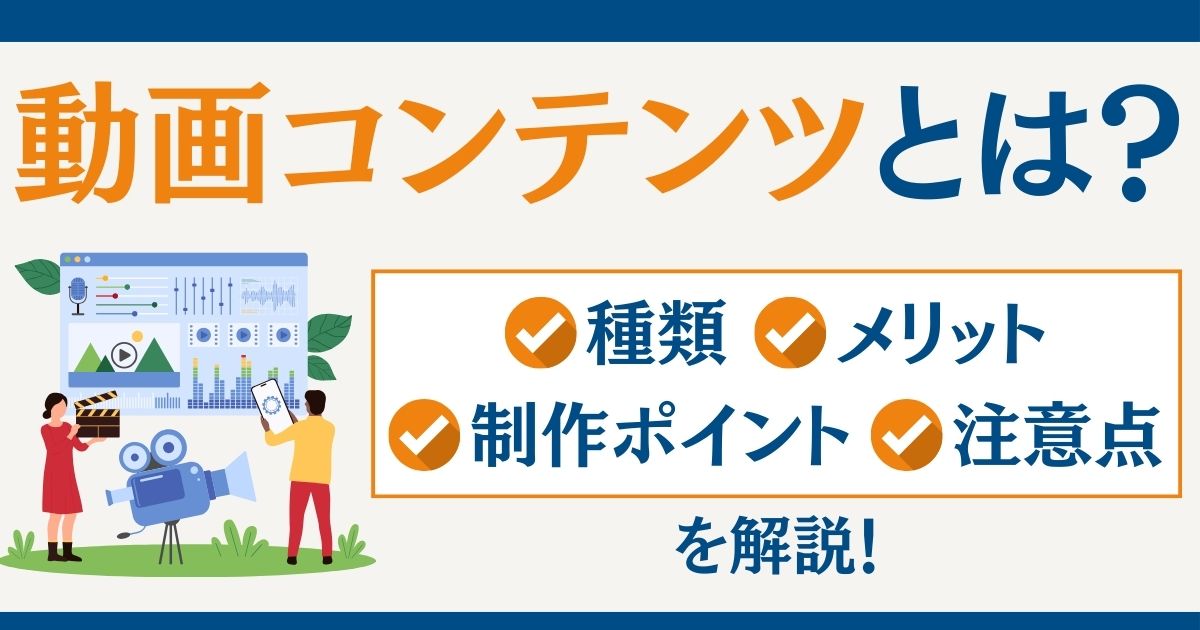動画コンテンツは現代のマーケティングにおいて重要な役割を果たしています。しかし、動画コンテンツのポイントや注意点を正しく理解していないと、効果的な活用はおこなえません。
この記事では、動画コンテンツの種類、メリット、制作のポイント、注意点などを網羅的に解説します。この記事を読むことで、動画コンテンツを効果的に活用するための知識を得ることができてマーケティング戦略の立案に役立たせられますよ。
ぜひ、最後までご一読ください。
動画コンテンツとは
近年、インターネットの普及に伴い、動画コンテンツは私たちの生活に欠かせないものになってきました。ビジネスシーンでもマーケティング戦略の一環として活用されるなど、その重要性はますます高まっています。この章では動画コンテンツの定義や現状、そして今後の展望について詳しく解説します。
動画コンテンツの定義
動画コンテンツとは、音声、映像、テキスト、アニメーションなどを組み合わせた動的なデジタルコンテンツのことをいいます。静止画やテキストだけでは伝えきれない情報をより分かりやすく、より魅力的に表現することが可能です。動画コンテンツはYouTubeやTikTok、Instagramなどの動画共有プラットフォームで視聴されるだけでなく、企業のウェブサイトやオンライン広告、教育コンテンツなどさまざまな場面で活用されています。
動画コンテンツの現状と将来性
スマートフォンの普及やインターネット回線の高速化に伴い、動画コンテンツ市場は急速に拡大していて、今後も成長していくと予想されています。
また、検索エンジン最適化(SEO)の観点からも動画コンテンツへの取り組みが不可欠となっています。動画コンテンツに適切なタイトルや説明文やタグなどを設定することで、検索結果の上位に表示されやすくなり、より多くの視聴者へアプローチすることが可能です。
今後の動画コンテンツ市場においては質の高い動画コンテンツ制作だけでなく、効果的なSEO対策も成功の鍵を握るでしょう。
動画コンテンツの種類
動画コンテンツはその目的やターゲット、プラットフォームによってさまざまな種類が存在します。ここでは代表的な動画コンテンツを紹介しましょう。
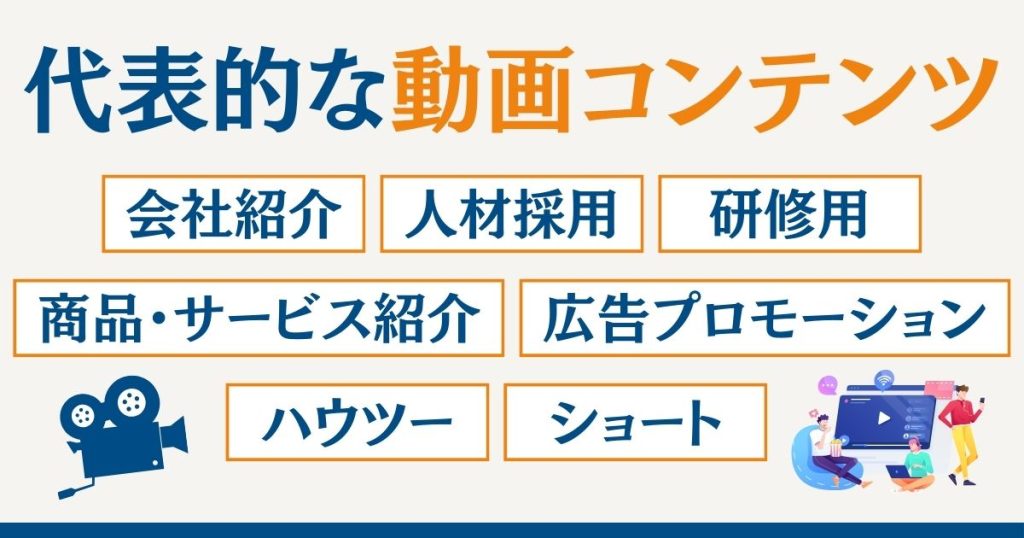
会社紹介動画
会社紹介動画は採用希望者や取引先に企業の理念やサービス内容などを伝えるための動画です。求職者や取引先に好印象を与えつつ、企業理解を深めてもらえるような動画を作ることが重要になってきます。
会社紹介動画はインタビュー形式、アニメーション、ドキュメンタリー風など、さまざまなやり方によって制作されます。
人材採用動画
企業の魅力や社風や仕事内容などを伝えて、求職者にアピールをおこなう動画です。企業の雰囲気や社員インタビューなどを盛り込むことで、よりリアルな情報を求職者に伝えることができます。
研修用動画
社員教育や研修に用いられる動画です。新入社員研修やスキルアップ研修やコンプライアンス研修など、さまざまな場面で利用されています。
商品・サービス紹介動画
商品やサービスの特徴や使い方、メリットなどを分かりやすく説明する動画です。商品やサービスの魅力を効果的に伝えて消費者の購買意欲を高めることを目的としています。実演動画やレビュー動画なども含まれます。
広告プロモーション動画
商品やサービスやイベントなどを広く宣伝するための動画です。テレビCMやWeb広告など、さまざまな媒体で配信されます。ターゲット層に訴求し認知度向上や購買意欲向上を図ることを目的として制作されます。
広告プロモーション動画にはストーリー性のあるものやインパクトのあるビジュアルを重視したものなど、さまざまな動画が作られています。
ハウツー動画
特定の作業の手順や方法を解説する動画です。料理のレシピやDIY、ソフトウェアの使い方など、さまざまな分野で活用されています。視聴者に手順のやり方や注意点を伝えることで上手に成果を得られることを目的として制作されます。
ショート動画
TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsなどのプラットフォームで配信される1分ほどの短尺動画です。短い時間でインパクトのある情報を伝えて視聴者のエンゲージメントを高めることを目的としています。手軽に視聴できるため幅広い層へのリーチが期待できるのが特徴です。
ショート動画には、ダンスや歌、コメディ、商品紹介などさまざまなジャンルのコンテンツがあります。
動画コンテンツのメリット
動画コンテンツは静止画やテキストコンテンツと比較して多くのメリットが存在します。ここではビジネスシーンでよく使用されている動画コンテンツに関してのメリットを解説します。

多くの情報を伝えられる
動画コンテンツは音声・映像・テキストを組み合わせることで、一度に多くの情報を伝えることができます。その量はなんと、文章と比較すると5000倍もの量を伝えられるんです。
さらに、アメリカの調査会社Forrester ResearchのJames L. McQuivey博士が2014年4月に発表した研究によると、「1分間の動画から伝わる情報量は文字に換算すると180万語、Webページに換算すると約3,600ページ分になる」とのことで、いかに動画コンテンツが情報伝達に効果的かわかりますね。
記憶に定着しやすい
人間の脳は視覚と聴覚を組み合わせた情報を処理する際に記憶が定着しやすいといわれています。動画コンテンツはまさにこの特性を利用しているので商品やサービスの情報を覚えてもらうのにうってつけの手段です。
商品名やサービス内容を覚えてもらうことを目的とした広告プロモーションにおいては、動画コンテンツを用いて記憶の定着を図るといいでしょう。
SNSで拡散されやすい
動画コンテンツはSNSで拡散されやすいというメリットがあります。特に短い動画はシェアされやすいだけでなく、口コミ効果によって多くの人の目に触れる可能性が高いでしょう。
さまざまなSNSで動画コンテンツが活用されており、企業のマーケティング活動においても重要な役割を担っています。魅力的な動画コンテンツを作成することで、ブランド認知度の向上や顧客獲得に繋げることが可能です。
動画コンテンツを見てから判断する人が多い
現代の消費者は商品やサービスを購入する前に動画コンテンツで情報収集をおこなうことが一般的です。
印刷・集客支援をおこなうラクスルの調査によると、消費者の約半数がショート動画を見て商品購入やサービスの利用をしたことがあるという結果が出ています。これは、商品レビュー動画やサービス紹介動画などを視聴することで、購入前に具体的なイメージを持つことができて購買意欲を高められるからと考えらえれています。
企業は消費者のニーズに応える質の高い動画コンテンツを提供することによって、消費者に購買行動を促進させることができるでしょう。
SEO効果が高く検索エンジンからの評価が上がる
動画コンテンツをサイトに載せることで、サイトの滞在時間が延びることや、ユーザーの利便性が高くなることから、SEOに対していい影響を与えられます。
また、アメリカ調査会社のForrester Researchは、「動画の埋め込まれた ページは、埋め込まれていない ページに比較して、約53倍の確率で検索結果の上位表示が期待できる」(2010年)という調査結果を出しています。
Googleの検索においても、動画コンテンツが検索結果の上位に表示されることが多くなってきており、ますます動画を用いたSEO対策の重要性が高まってくるでしょう。
動画サイトマップの送信や適切なキーワード設定、魅力的なサムネイル画像の設定などの動画SEO対策を施すことによって、ウェブサイトへの導入数増加を目指せるでしょう。
| メリット | 詳細 |
| 情報量の多さ | テキスト、画像、音声による情報伝達で理解を深める |
| 記憶への定着 | 視覚と聴覚の相乗効果で記憶に残りやすい |
| 拡散性 | SNSでのシェアによる口コミ効果で広範囲にリーチ可能 |
| 購買意欲向上 | 商品やサービスの理解促進で購買行動を後押し |
| SEO効果 | 検索エンジン最適化でウェブサイトへの流入増加 |
動画コンテンツ制作のポイント
動画コンテンツを制作する上で重要なポイントを企画・撮影・編集の3つの工程に分けて解説します。クオリティの高い動画を制作するためにも、各工程で押さえるべきポイントをしっかりと理解しましょう。
それではそれぞれのポイントをお伝えします。
企画
動画制作の最初の工程である企画段階では、目的・ターゲット・動画の種類を明確にすることが重要です。目的が明確でないと動画の方向性が定まらず、視聴者へしっかりとメッセージを伝えられなくなります。
また、ターゲットを明確にすることで、誰に対してどのような動画を制作するべきかが分かってきます。動画の種類は目的に合わせて適切なものを選択しましょう。
それでは、企画設定に必要な
・目標の設定
・ターゲット・ペルソナの明確化
・動画の種類の選定
のポイントをお伝えします。
目的の設定
動画を制作する目的を明確にしましょう。「商品やサービスの認知度向上」、「販売促進」、「企業イメージの向上」など目的はさまざまです。動画作成の目的が明確であれば、動画の内容も自ずと決まってきます。
ターゲット・ペルソナの明確化
動画を見てもらいたいターゲットを明確にしましょう。年齢・性別・職業・興味関心などを具体化してターゲットを絞り込むほど、効果的な動画制作が可能になります。
また、ターゲットが決まった後にペルソナを設定することで、より消費者の深層心理を把握することが可能となるでしょう。
詳しくはこちらの記事をご一読ください
動画の種類の選定
目的に合わせて最適な動画の種類を選びましょう。それぞれの動画の種類の特徴を理解し、目的に合った動画を選択することが重要です。
撮影
撮影段階では機材の準備、撮影場所の選定、ライティングなど、さまざまな要素に注意が必要です。高品質な映像を撮影するためには事前の準備が欠かせません。
それでは、それぞれの工程について詳しく説明します。
機材の準備
動画撮影に必要な機材を準備しましょう。カメラ、三脚、マイク、照明など、機材の性能によって動画のクオリティが大きく左右されます。予算に合わせて適切な機材を選びましょう。
撮影場所の選定
動画の内容に合った撮影場所を選びましょう。屋内、屋外、スタジオなど、撮影場所によって動画の雰囲気が大きく変わります。
周囲の音や光にも注意が必要です。騒音の少ない場所を選んで自然光を活かせる環境を作るか、もしくは適切な照明器具を使用することによって、より質の高い映像を撮影できます。
ライティング
適切なライティングをおこなうことで、動画の見栄えが格段に向上します。自然光を利用する場合は、時間帯によって光の当たり方が変わるため注意が必要です。照明器具を使用する場合は被写体に合わせて明るさや色温度を調整しましょう。
編集
撮影した動画素材を編集することで効果的な動画コンテンツに仕上げられます。動画編集ソフトの選択・効果音やBGMの追加・テロップ挿入など編集作業は動画制作において重要な役割です。
以下に詳しい工程を解説していきます。
動画編集ソフトの選択
動画編集ソフトにはAdobe Premiere Pro、Final Cut Pro X、Filmora、iMovieなどさまざまな種類があります。自身のスキルや予算に合わせて最適なソフトを選びましょう。無料ソフトでも十分な編集機能を備えているものもあります。
効果音やBGMの追加
効果音やBGMを追加することで動画の雰囲気を高めることができます。動画の内容に合った効果音やBGMを選び、視聴者の感情を揺さぶるような演出を心がけましょう。フリー音源サイトなどを利用すれば、著作権フリーの音源を無料でダウンロードすることが可能です。
テロップ挿入
動画の内容を理解しやすくするためにテロップを挿入しましょう。重要なキーワードや説明などをテロップで表示することで、視聴者の理解を促進することができます。テロップのフォントや色、表示時間にもこだわり、動画全体の雰囲気と調和させることが大切です。
| 工程 | ポイント | 詳細 |
| 企画 | 目的の設定 | 動画の目的を明確にすることで、方向性が定まり、視聴者にメッセージが伝わりやすくなる。 |
| ターゲット・ペルソナの明確化 | ターゲットを絞り込むことで、より効果的な動画制作が可能になる。 | |
| 動画の種類の選定 | 目的に合わせて適切な動画の種類を選択する。 | |
| 撮影 | 機材の準備 | カメラ、三脚、マイク、照明など、動画撮影に必要な機材を準備する。 |
| 撮影場所の選定 | 動画の内容に合った撮影場所を選び、周囲の音や光にも注意する。 | |
| ライティング | 適切なライティングをおこなうことで、動画の見栄えが格段に向上する。 | |
| 編集 | 動画編集ソフトの選択 | スキルや予算に合わせて最適な動画編集ソフトを選ぶ。 |
| 効果音やBGMの追加 | 動画の内容に合った効果音やBGMを選び、動画の雰囲気を高める。 | |
| テロップ挿入 | 重要なキーワードや説明などをテロップで表示することで、視聴者の理解を促進する。 |
これらのポイントを踏まえ、質の高い動画コンテンツを制作し、ビジネスの成功に繋げましょう。
動画コンテンツ制作における注意点
動画コンテンツを制作する際には、いくつかの法的および倫理的な注意点を守ることが重要です。これらを怠ると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。主な注意点として著作権、肖像権、個人情報保護、そして表現に関する配慮が挙げられます。
ひとつずつ詳しくお伝えします。
著作権
動画コンテンツ制作において著作権は重要な注意点の一つです。著作権とは創作物を作成した人に与えられる権利です。動画内で使用する音楽、画像、動画素材、フォントなどが他者の著作物である場合、無断で使用することは著作権侵害に当たります。
肖像権
肖像権とは個人が自分の容姿を無断で撮影・公開されない権利です。動画に人物を登場させる場合は、必ず事前に本人の許可を得る必要があります。
街頭インタビューなどで不特定多数の人物を撮影する場合でも、個人が特定できるような形で公開することは避けるべきです。撮影許可を得る際には、動画の用途や公開範囲などを明確に説明するようにしましょう。
個人情報保護
動画内で個人が特定できるような情報を公開する場合、個人情報保護法に則って適切な対応をする必要があります。氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報は、本人の同意なしに公開することはできません。
インタビュー動画などを公開する際には、個人が特定できる情報を編集で削除するか、モザイク処理などで匿名化するなどの配慮が必要です。
表現に関する配慮
動画コンテンツは多くの人に見られる可能性があるため表現には十分な配慮が必要です。特定の個人や団体を誹謗中傷するような内容、差別的な表現、わいせつな表現などは避けるべきです。
また、未成年者が出演する動画の場合、青少年保護育成条例などに抵触しないよう注意する必要があります。表現の自由は保障されていますが、他者の権利や尊厳を侵害するような表現は許されません。
| 注意点 | 詳細 | 対策 |
| 著作権 | 音楽、画像、動画、フォントなど、他者の著作物を無断で使用すること。 | 著作権フリー素材の使用、著作権者からの許諾取得、適切なクレジット表記。 |
| 肖像権 | 個人の容姿・姿態を無断で撮影・公開すること。 | 撮影・公開前に本人の許可を得る、個人が特定できないように配慮する。 |
| 個人情報保護 | 氏名、住所など個人が特定できる情報を無断で公開すること。 | 個人情報の公開前に本人の同意を得る、匿名化処理をおこなう。 |
| 表現に関する配慮 | 誹謗中傷、差別的表現、暴力表現、わいせつ表現などをおこなうこと。 | 倫理的に問題のある表現は避ける、関係法令を遵守する。 |
これらの注意点を守って適切に対応をすることによってトラブルを未然に防ぎ、視聴者から信頼される動画コンテンツを制作することができます。動画制作の際は常にこれらの点を意識しつつ責任ある行動を心がけましょう。
動画コンテンツの活用事例
動画コンテンツはさまざまなプラットフォームで活用できます。それぞれのプラットフォームの特徴を理解して適切な動画を配信することで、より大きな効果を得ることが可能です。
ここでは、代表的なプラットフォームにおける動画コンテンツの特徴を紹介します。
YouTube
YouTubeは世界最大の動画共有プラットフォームであり、あらゆる種類の動画コンテンツを配信するのにピッタリです。企業アカウントを作成して自社のチャンネルを持つことで、ブランド認知度の向上や見込み顧客の獲得、顧客ロイヤリティの向上などに繋げることができます。
YouTubeではSEO対策を施したタイトルや説明文やタグを設定することで、検索結果の上位に表示されやすくなりますよ。
また、チャンネル登録者数を増やすことで、動画の視聴回数を伸ばすことが可能です。さらに、視聴者からのコメントに返信するなど、積極的にコミュニケーションを取ることでエンゲージメントを高められるでしょう。
TikTok
TikTokはショートムービープラットフォームであり、短い動画でユーザーの興味関心を惹き付ける必要があります。若年層を中心に利用者が多く、トレンドに敏感なユーザーが多いのが特徴です。音楽やダンス、 humorを取り入れた動画コンテンツが人気を集めています。
TikTokはハッシュタグを効果的に活用することで、より多くのユーザーに動画を届けられるでしょう。インフルエンサーとコラボレーションすることでより多くのユーザーにリーチすることもできるでしょう。
Instagramは写真や動画を中心としたSNSであり、ビジュアルでユーザーに訴求することが重要です。高画質で美しい動画や、ストーリー機能を活用した短い動画が効果的です。
また、ライブ配信機能を使って、フォロワーとリアルタイムでコミュニケーションを取れます。
Instagramはハッシュタグや位置情報を活用することで、より多くのユーザーに動画を見てもらうことが可能です。
また、ストーリーズ機能で質問ステッカーやアンケート機能を活用することで、フォロワーとのエンゲージメントを高められます。ショッピング機能と連携させることで、動画から直接商品購入ページへ誘導することも可能です。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)はリアルタイムな情報発信に特化したSNSであり、短い動画でユーザーの注目を集めることが重要です。ニュース性のある動画や、ユーザーの共感を呼ぶ動画が拡散されやすい傾向にあります。また、ライブ配信機能を使って、リアルタイムで情報を発信することも可能です。
X(旧Twitter)はインフルエンサーや他のユーザーをメンションすることで拡散力を高めることができます。リツイートやいいね、コメントを促すような呼びかけをすることも効果的です。
まとめ
この記事では、動画コンテンツの内容や制作のポイントなどをお伝えしてきました。
目的に合った動画コンテンツを選択しつつ、ハッシュタグなどを用いながらエンゲージメントを高める施策が必要になってきますね。
また、『ontsuigi』では、InstagramやTikTokやYouTubeをはじめとしたSNS運用で困っている企業様や担当者様に対してゴール達成に繋がるようなSNS運用のご支援を行っています。
少しでも気になる企業様は、この記事を読んだ後すぐに企業向け無料診断をチェックしてみてください!